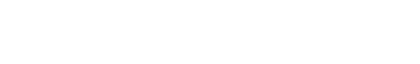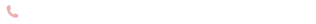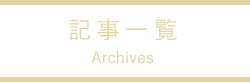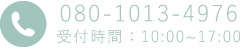体調管理も大事ですね
4月に入ったというのに、冷たい風でした。
少しずつ暖かくなっていはいますが、
日によっては気温差が激しく、
ただでさえ体調管理が難しいと感じます。
本番が近いので、
いつもにも増して体調に気を付けないと!と、神経を使います。
しかし、あまり気にしすぎるのもよくないし、それまでは日常の生活があるので、かえって本番の日には疲れがでてしまってはいけないし、、、、
これも、経験を積むことで、どんな風に過ごしたら良いのか、やってみないと分からないことがありますね。
結婚してからは、本番前に気を付けることが増えました。
料理をするときの包丁の扱いです。
うっかり指を切ってしまうこともあるので、本番が近くなると、慎重に料理をするようになります。
前日などは、包丁をなるべく使わないようにするとか、
本番当日はなるべく水をさわらないようにするとか、
水をさわりすぎると、指先が乾燥してしまって、鍵盤をつかむことが出来なくなるのです。これは学生時代には全く気にしたことがありませんでした。
そうはいっても、ピアノの場合はまだ体調管理はしやすいと思います。
声楽の方だと、からだが楽器ですから、ちょっとでもどこかに不調があると、直に声に影響がでるし、普段から喉を酷使しているので、本番前だからといって、急にハードな練習をすると、喉が疲れてしまって、肝心の本番に声の調子が悪くなることもあるそうです。
どのくらいのペースで練習するかも、難しそうですね。
それにくらべるとピアノは調整がしやすいのかなとも思います。
あと、気を付けたいのは爪です。
普段からピアノを弾くときは爪を気を付けていますが、直前に切り揃えるのは控えています。
気にしすぎて、切りすぎてしまうと、深爪の状態になり、演奏するときに痛くなってしまいます。
それを避けるためにも、2・3日まえに切り揃えておくと良いでしょう。
本番に穴を空けることは絶対に出来ないので、演奏の準備だけでなく、体調を万全に整えるという準備もとても大事ですね。
2021年04月09日(金) │ ブログ
正しいフォームは弾きやすい!
子どもたちの指って
小さくて、ぷくぷくっとしていて、
とても可愛らしいですね。
私のゴツゴツした指と比べたら
細くて、柔らかくて
すぐ折れてしまいそうです。
まだまだ小さい手のうちは
指を一本一本独立させて、
体重をかけた演奏は筋力的に難しい面があります。
ハノンなどを使ったテクニックのトレーニングは小学3年生ぐらいから始められますが、やはり最初から正しいフォームで演奏したいですね。
腕の力で鍵盤を押さえるような弾き方になることが多く、手首が鍵盤よりも下がって弾いてしまうことがあります。
すると、指先は鍵盤に残っているので、鍵盤にぶら下がった状態になります。
そうなると、指先を自由に動かすことができずに、ぎこちない動きになってしまいます。
最初のうちはその弾き方でもなんとか間に合いますが、だんだん曲の難易度が上がってきて、音符の種類も増えてくると、八分音符などの早い動きを粒をきれいに揃えなくてはいけません。
この段階で、手首を鍵盤よりも下に下がった状態だと、逆に弾きづらくなります。
理想的な手首の位置は、鍵盤と同じ高さに揃えることです。すると指先が自然なカーブを描き、第3間接が一番高い山のようになります。
よく卵をつかむような手の形と言われませんでしたか?ギュッと握ってしまうと、卵がつぶれてしまうので、ソッとつかむような形が理想的です。
この形にして、第3間接から指を動かすようにすると、指が一本一本独立して動かすことができます。
無理な力を加えることなく、自然な腕と指の重さで鍵盤を押さえることになり、芯があって、よく伸びる音がでるようになります。
早く走るために、足を高くあげて走るような感じと言い換えることができるでしょうか?鍵盤の上を指がはっきり動くようなイメージです。
歩き方に例えて話すこともあります。
ちょっと弾きづらいなと感じるときは、手のフォームを見直してみることをおすすめします。
指の先を意識して鍵盤に触れるようにしてみましょう。欲しい音色の音を出すための第一歩です。
2021年04月09日(金) │ ブログ